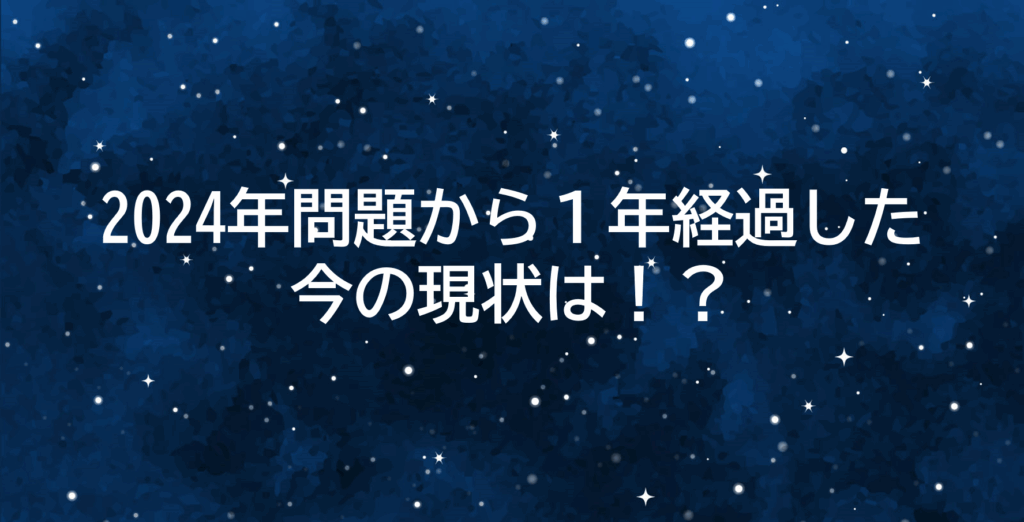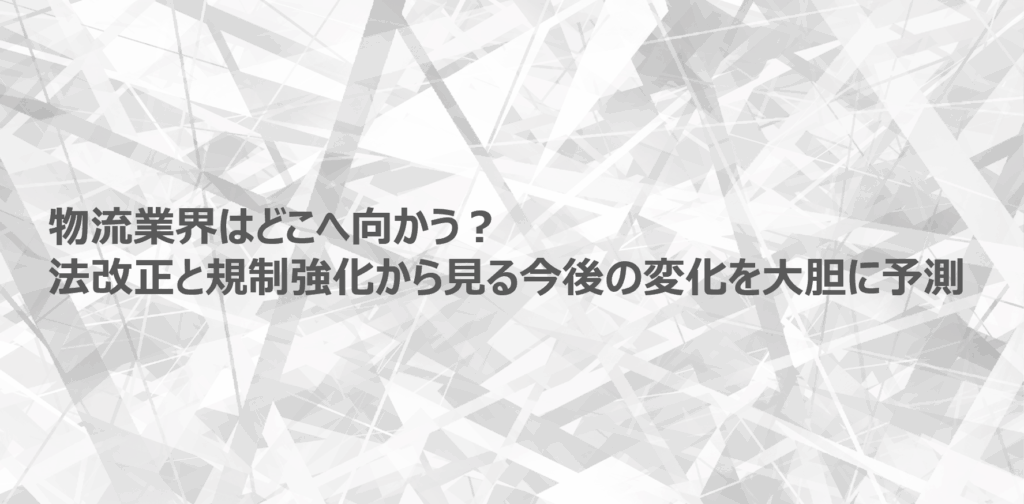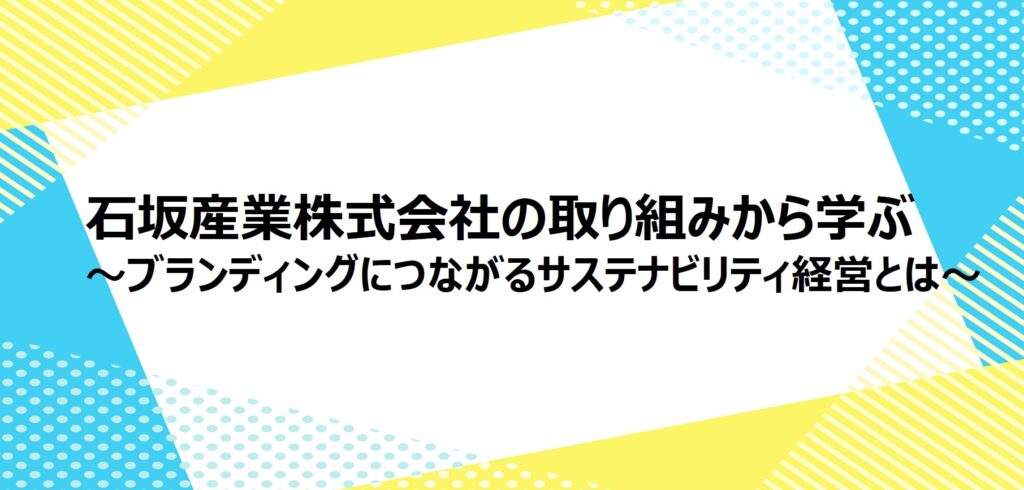FCVと水素ステーション普及に関する現状と課題について~脱炭素社会の実現に向けて~
こんにちは!日野コンピューターシステム株式会社(HCS)のブログへようこそ。
今回は、脱炭素社会の実現に向けた話題を提供します。近年、水素を燃料としたFCVの普及が期待されています。一方で、国が掲げる普及に関する目標値からは大きく乖離しており、FCV普及が進んでいないのが現状です。本記事では、FCVとそのインフラである水素ステーション普及に関する現状と課題について解説します。
1. 日本のカーボンニュートラルと自動車
日本は2050年にカーボンニュートラルの達成に向け、2030年度46%削減、2035年度60%削減、2040年度73%削減 (2013年度比) の目標を掲げて脱炭素社会の実現を目指しています。

出展:外務省『気候変動 日本の排出削減目標』より弊社作成
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000121.html
また、日本国内における二酸化炭素排出量のうち、17.7%を運輸部門が占めており、カーボンニュートラル社会の実現に向けては運輸部門の脱炭素化が不可欠であり、早急な対応が求められています。
2. FCVとはなにか?
FCV(Fuel Cell Vehicle)とは燃料電池自動車の略であり、水素と酸素の化学反応で発電した電気をバッテリーに貯め、その電気でモーターを回して走る自動車のことをいいます。みなさんも化学の授業で体験したことがあると思いますが、水素と酸素を化学反応させると水が生成されるので、非常にエコであるという訳です。
トラックのライフサイクルにおけるCO₂排出量のうち走行時が約9割を占めると言われています。走行距離が長く、その積載重量からBEV(電気自動車)では対応ができない大型トラックや大型バスではFCVが注目されています。
日本国内では、日野自動車とトヨタ自動車によって共同開発されたFCV大型トラック「日野プロフィア Z FCV」が現在走行実証を通じて実用化に向けた取り組みを推進中です。HCSも日野自動車グループなので非常に注目しています。
参考:「燃料電池大型トラックの走行実証を2022年春頃より開始」-日野自動車
https://www.hino.co.jp/corp/news/2020/20201013-002705.html
3. FCVと水素ステーションの普及に関する計画と実現
経済産業省では、2030年までに乗用車換算で80万台程度(水素消費量8万トン/年程度)のFCVの普及目標を掲げています。一方で、現状は目標値からは大きく乖離しています。
特にFCトラックの普及が進まない理由として「三すくみ状態」が課題として挙げられています。
自動車メーカーはFCVの開発に向けて需要が見込まれないと投資計画が立てられず、運送企業・荷主企業においてはFCVの生産見込みと水素ステーションの普及が拡大しないと導入計画が立てられません。また、水素ステーションを設置するインフラ企業はFCVの導入数がわからないと投資計画が立てられない。といったように、各ステークホルダーがそれぞれの課題に直面し、「三すくみの状態」になっているということです。
4. 水素ステーション整備における課題
水素ステーション普及に関してもFCV同様、経済産業省が掲げる目標値「2030 年度までに1,000基程度の整備」に対し、現状は目標値からは大きく乖離しています。
普及が進まない原因のひとつに「需要と供給の不一致」があり、想定よりも需要が見込まれなかったことによるステーションの閉鎖事例もあります。「需要と供給の不一致」を起こさないためには、整備計画段階で物流の需要を的確に把握し、最適な場所に配置することが重要です。
経済産業省も、『モビリティ分野における水素の普及に向けた中間とりまとめ』にて「水素ステーションも人流・物流を考慮した最適配置、大型化を進める」、「需要の把握が水素ステーション整備の方針の決定にあたって極めて重要」としており、人流・物流を考慮したステーションの需要把握が求められていることが分かります。
5. まとめ
カーボンニュートラル実現に向けてFCVは必要不可欠な技術のひとつであり、その普及を進めるためには「三すくみ状態」を打破することが重要な要素のひとつです。
水素ステーションの需要把握は、日野自動車製トラック・バスから取得できるコネクティッドデータを分析することで物流の動きを可視化し、さらには水素ステーションの需要を予測することで最適なインフラ設置場所を提案することがHCSでは可能です。この分析レポートは福岡県様にも導入いただきました。HCSではこの他にもコネクティッドデータを活用したサービスを展開していますので、なんなりとお申し付けください!
関連商品:日野コネクティッドデータサービス
この記事を書いた人
日野コンピューターシステム株式会社 ソリューション推進部 三好